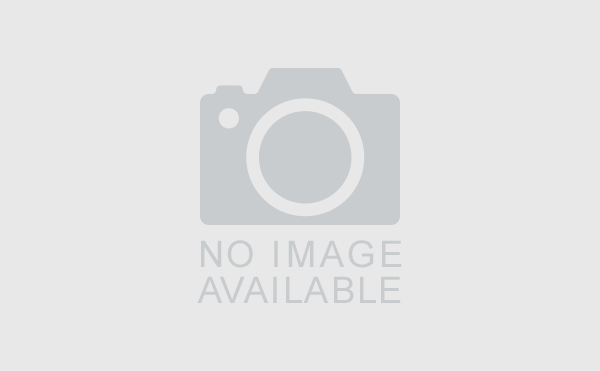操体臨床の未来像(ビジョン)・操体臨床の新なる真価
操体臨床の未来像(ビジョン)・操体臨床の新なる真価
操体法を体系づけるきっかけとなったと言われる高橋迪雄氏の正体術に、橋本先生が出会ったのは、函館で開業されておられた一九三三年~一九三四年(昭和8年~9年) 三十六、七才の時と伺っている。その当時をふりかえり、先生は、次のように述べている。「楽なほうに動かして治るんならばそれにこしたことはない」、「いたく興味を引かれた」と、お聴きしている。のちに先生は医師の立場から、運動系の歪みに着眼さ れ、疾患現象をボディーの歪みという異常状態から構造運動力学的に把握し臨床としての可能性を確立されてこられたのである。
この正体術に関する本が私の手元にも何冊かある。その技法と言うよりも、診断と操法上の行程において、操体法と正体術との類似する点がどこにあるのかを、興味深く目をとおしてみたことがある。私が師の元で学んだ修行時代(1966~1971)その区別がつかぬほど正体術と類似していたのであった。
当時は操体という名称すら無かった。先生は「名称など、どうでもいいことだ、真理が大切なんだ」と、いっこうに気にとめる風でも無かった。やっと操体と名称したのは師七十九歳、1975年の年であった。(その当時はまだきもちのよさ、その快適感覚で治るという、快適感覚そのものに対する操体の考え方は無かったと思われる)
「類似していた」、と言うことは、先生は正体術をそっくり、そのまゝ有難く頂だいしていたのである。診断における、動診の問いかけも、
・対なる動きを二極に対比させ、二者択一的にどちらが楽か辛いかの運動感覚差をききわけている。 操法上、
・楽な動きを歪み整復の復元運動コースと定めている ・楽な動きの可動極限においてたわめの間を設定獲得している
・脱力の仕方も瞬間急速脱力に導いている、回数の問いかけも、形式上、正体術そのものなのである。
これが、従来おこなわれつづけて来た操体法の姿なのである。
操体は正体術にヒントを得ている。その診断と操法において、共通し類似していることも事実で「操体の源流」とも言える。ならば我々は先生が正体術との出会いの中で、何をつかみ、どうしようとされたのか(されようとなさったのか)その成そうとされてきたこと、成したることを明確に示していく責任がある。
明確に正し示していくことが、正体術と操体法のさらなる発展に継がり未病医学という医の原点(日本医学)に立ち帰える源動力そのものの姿が、天望できるはづなのである。
正体術と操体法はいわば、切っても切れない兄弟関係にある。兄の恩恵を受け、操体を学んでこれたのである。我々、弟はその恩恵に敬意と礼をもって尽くすべきである。尽くすとは、師の成したること、成さんとしてきたことの真意を悟りよりよく修学していくことではないか!
操体の臨床は快適感覚そのものに対する診断と操法が確立されて初めて、操体が操体として自立できた、と公言できるのではなかろうか。
楽な動きを快コースと定め上記の操法の行程を今もなほ、これぞ操体と、真(まこと)しやかに実践されている同志よ、実は、実践してきたことが正体術そのものであった、ということに気づきをもつべきではなかろうか。
その後、師は、操体の臨床の中で、操法としての快コースの設定に新たなる展開をみせている。
その(1)動診の設定
二極対比の分析法にとどまってはいるが、動診の目的を「きもちのよさをききわけること。」と明確にされておられる。「楽な動きをききわけよ」とは発言されていない。 正体術は二極対比、あくまで らくな動きの確認である。
その(2)快方向(快コース)の設定
操体では、快適感覚を快コースに定める、正体術は、らくな動きを快コースに定める
その(3)たわめの間の設定
快の極点、つまり快感のきわまり、最もきもちがよいところで たわめの間を獲得するようになった。 正体術では、楽な動きの可動極限においてたわめの間を設定している。
その(4)脱力の設定
2~3秒間のたわめの間ののちに瞬間急速脱力に導く。正体術も同様である。
その(5)回数の設定
SOTAIも、正体術も2~3回と同じ ・この(4)と(5)も改正されなければならない
・従来のSOTAIと正体術の盲点の指摘
その(1) 「からだの要求感覚」(生命感覚、命の意志)にききわけるという気づきが無い。
SOTAIでは快適感覚を重視するが、楽感と快適感覚を混同し 同質にとらえている傾向がある。
その(2) 操法の選択としてからだは、快適感覚を要求し選択してくる。決して楽感覚を選択してこないのである。つまり、操法上、からだが要求してくる快と操者が選択する快とが常に一致していない。なぜなら操者は楽な動きを操法として選択するからである。それはつまり、楽な動きに、快適感覚が有る場合と無い場合があり、無い場合のほうが多いからである。
(ただ単に楽でスムースな場合)
その(3) 2~3秒のたわめのマの設定においてからだの要求感覚にききわけると、たわめの間の時空は、きもちのよさ、その快感度が高ければ高いほど、たわめのマの時空が長いことが分かった。 逆に、快感度が低ければ低いほどたわめのマが非常に短かいことがわかった。 楽な動きに快適感覚がない場合、2~3秒間のたわめのマがだとうである。だとうで はあるが、全身急速脱力ができない患者がでてくる。脱力のさせ方に工夫が必要となる
その(4) 操法の回数に対して、からだの要求感覚にききわけると、快感度が高ければ高いほど からだは回数をあえて要求してこないことが分かった。(一回で十分である) ※操法の回数及び、脱力の方法に対して
・操者の指示によるものなのか
・患者の要求によるものなのか
・からだの要求感覚をききわけてのものなのかを明確にすべきである。
今までは、操者の指示によるものであった。これからはからだが要求し選択してくる脱力の仕方や、操法の回数を考慮すべきである。
今後の課題として
1. 操体にしろ、正体術にしと、最大の弱点は、動診がとおせない患者や、感覚がききわけられない患者(特にからだが要求してくる、きもちのよさ、その快適感覚がわからない患者)にどう対処するのか。その診断と操法の問いかけがないことである 。
2. 動診してみれば、快方向(快コース)が、必ず確認できるのか!確認できないケースが存在することがある。症状疾患の状況によっては、どう動かしても、痛覚がある、 どう動かしてもつらい、痛い場合がある。つまり八方塞 がりのケースである。八方塞がりとは、からだの要求感覚として、からだの動きを 八方に塞いで安静を求めている、ということである。その場合、どう対処するのか!
3. SOTAIは痛み(ペイン)には効果があるが疾患には効果がない、と公言する30年近くSOTAIをおこなっている人もおられる。なぜそう公言できるのか。
4. 内臓疾患をかかえた患者にSOTAIをおこなうと、かえって悪化するという麻酔科の先生もいる。手術後、いきなり横紋筋をゆるめると内臓を包括する不随意筋のバランスがとれなくなるという。 なぜなのか?
楽な動きと快適感覚との判別を操者が認識する必要性が必ず生じてくる。
——————————————————————————–
・従来の操体が快適感覚に元づく、診断と操法に生まれ変わるためには、従来の操体法が次のように改正されてくる。
1▼動診は、楽か辛いかの運動感覚差の聞き訳ではなく、快適感覚そのものに対する聞きわけとなる
当然、その診断も、対なる動きを二者択一的に分析するのでは無く、1つ1つのどの動きに、快適感覚が確認できるかの、一極微(いちごくみ)の分析法と成る。
〔例〕首の分析をとおす場合は、首の前屈と後屈の運動分析とはならず、
・首、前屈の感覚分析
・首、後屈の感覚分析、となる。
※感覚を確認するのであるから、運動分析ではなく感覚分析となる。
2▼快コースの設定
おのずとその設定も、快適感覚を快コースに定める。ただし、快適感覚にも快感度の質的条件がある
最もよき条件は、からだが要求し、選択してくる、きもちのよさを快コースに定めることである。
(からだにききわけて、味わってみたいという要求感覚を満してくるきもちのよさを快コースに定める)
3▼たわめの間の設定
快の極点、つまり快感のきわまり、(最もきもちがよいところ)で獲得する。
4▼たわめの間の設定
快感度によってその時空は一定では無い。一律に2~3秒と定めるのでは無く、きもちのよさが消えるまで、あるいはたのちに、あるいは、十分に味わって納得するまで、たわめの間を設定するのが望ましい。
5▼脱力の設定
瞬間急速脱力と一律に指示するのでは無く、からだが要求し選択してくる脱力の仕方に、委ねる、脱力方法となる。
6▼操法の回数の設定
もう一度味わってみたい要求があるのか無いのかをからだにききわけさせてみて 有ればもう一度とおしてみる。
※からだの要求感覚に従って操法の回数を決める、という、選択方法となる。
7▼動診がとおせない患者、又快適感覚のききわけがむずかしい患者、さらに、からだ そのものが、動きに快適 感覚をつけてこない場合、(つけていない場合)皮膚に快適感覚をききわける分析法を、考慮する必要がでてきた。その分析方法は可能になった。
8▼皮膚に快適感覚をききわけさせると錐体外路系への問いかけがより、強力になっ た。そのことによって、動きに問いかけた快適感覚とは異質なる快の存在が確認できた。その快を、生命感覚の快と名称した。
9▼快方向(快コース)を診断する分析方法が今まで、二者択一に対なる動きを比較対照し、楽か辛いかの確認法だけにとどまっていたが、現在8種類の分析法が可能になった。
快適感覚をききわけ、きもちのよさの最高をとおすのがSOTAIの臨床なのである。
からだは快の選択において、運動感覚差としての快(楽な動き)を求めているのではなく、生命感覚としての
快 (治癒力、恒常性に必要な快) を求めてくる。
生命感覚としての快を操法に とおすのが操体の臨床である。(イノチに必要な快を求めてくる。)
(2003年10月改訂) 東京操体フォーラム小冊子「Vision S」Vol.1掲載
橋本敬三先生の墓前にて